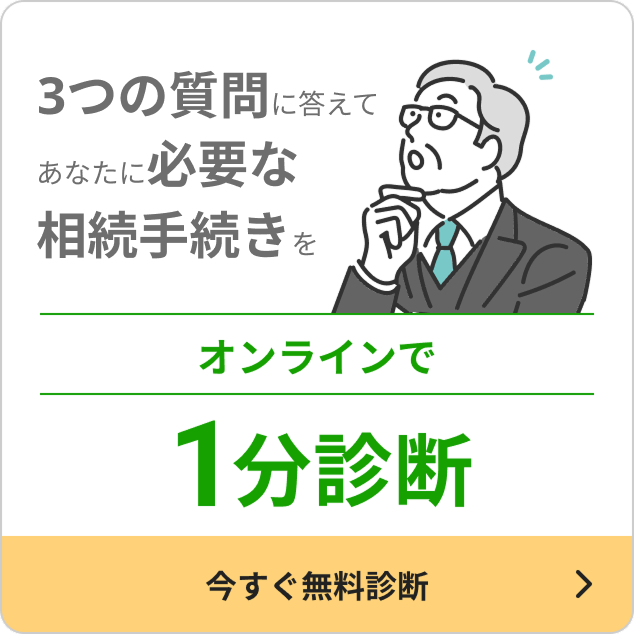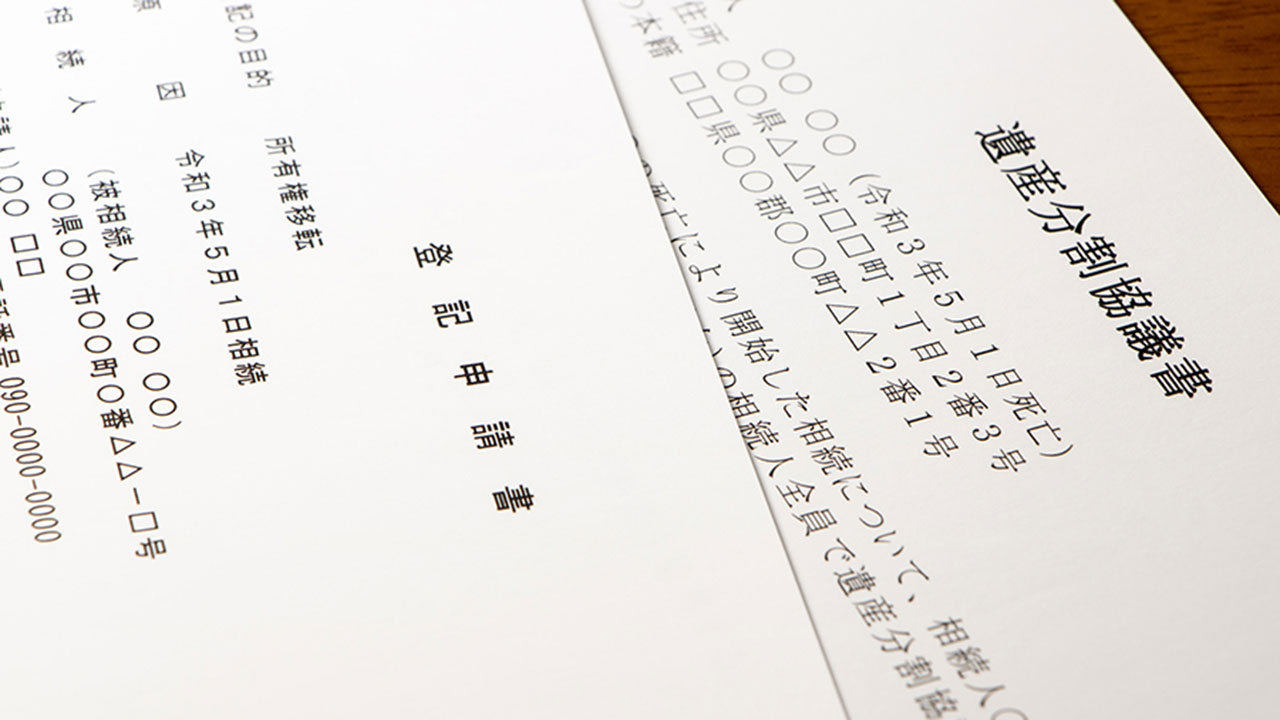寄与分とは?計算方法や認められるまでの流れや要件や時効
更新日

「何かと尽くしたのに、何もしなかった兄弟たちと同じ相続分なんて…。」と人知れず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そのような故人への貢献を正当に評価し、公平に相続財産を分けるために寄与分制度があります。
この記事では、寄与分の正当な評価を受けて寄与分を当然に得るための最重要知識9選をお伝えします。
是非、参考にしてください。
目次
寄与分とは?
寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。
寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。
民法(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
寄与分の計算方法
例えば、被相続人の2人の子AとBが相続人であったとします。
Aは被相続人の事業を無償で手伝い、Aには1,000万円の寄与分があるとします。Bには寄与分はないものとします。
相続財産が3,000万円であった場合、AとBの相続分は次のように算定します。
まず、実際の相続財産3,000万円から寄与分1,000万円を差し引いて、残った2,000万円が遺産分割をするうえで基礎となる相続財産(みなし相続財産)となります。
AとBの法定相続分は2分の1ずつなので、みなし相続財産の2,000万円を2分の1ずつ分割します。
そうすると、AとBの相続分は1,000万円ずつになります。
そして、Aには1,000万円の寄与分があるので、1,000万円の相続分に、1,000万円の寄与分を加え、Aの取得分は2,000万円となります。Bには寄与分はないため、Bの取得分は1,000万円です。
寄与分が認められるまでの流れ
寄与分が認められるまでの流れは次の通りです。
- 相続人間で協議
- 調停
- 審判
- 即時抗告
相続人間の協議
寄与分を見てもてもらいたい場合は、まずは、相続人間の協議の中で主張します。
他の相続人にとっては、寄与分を認めると、その分、自分の取得分が減るので、そう簡単に認めてもらえるとは限りません。
相続人間の協議がまとまらない場合や、そもそも協議ができない場合は、調停を申し立てることができます。
調停
調停で寄与分を協議する方法には、次の3つあります。
- 「寄与分を定める処分調停」において協議する方法
- 「遺産分割調停」の中で寄与分について協議する方法
- 「遺産分割調停」と「寄与分を定める処分調停」の両方を申立てて併合して協議する方法
通常は、両方を申立てて併合することをお勧めします。
調停で協議が調わなかった場合は、審判に移行するのですが、寄与分を定める処分調停しか申立てていない場合は、遺産分割審判の申立てをしなければ、不適法として却下されてしまうのです。
また、遺産分割調停しか申立てていなかった場合は、遺産分割審判に移行します。
審判
遺産分割審判では寄与分については審判されません。
調停が不成立になった場合に、スムーズに審判に移行し、寄与分についての審判を受けるためには、寄与分を定める処分調停と遺産分割調停の両方を申立てておいた方がよいのです。
即時抗告
そして、審判の結果に不服があるときは、審判結果の告知を受けた日の翌日から2週間以内に高等裁判所に対して即時抗告を行うことができます。
このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
寄与の要件

寄与分が認められるのは相続人だけ
まず、大前提として、寄与分は相続人にしか認められません。受遺者等の相続人以外の人には、寄与分は認められないのです。
他の相続人が認めてくれるなら法定の要件は関係ない
それでは、寄与分はどのような場合に認められるのでしょうか?前述の通り、寄与分は、まず、相続人間で協議されるので、その協議で認められればよいということになります。
ですので、必ずしも何らかの要件を満たしていなければ認められないものではなく、他の相続人が認めてくれさえすればよいのです。
もっとも寄与分を認めると、その分、自分の取得できる財産が減るので、そう簡単には認めてもらえないでしょう。
寄与の方法・型についての分類
まず、寄与の方法について、次の例が挙げられています。
- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 被相続人の事業に関する財産上の給付
- 被相続人の療養看護
これらに限らず、「その他の方法」でも構いません。
寄与の5つの型
分類すると、次の5つの型があるとされています。
- 家事従事型
- 金銭等出資型
- 療養看護型
- 扶養型
- 財産管理型
これら5つのいずれかに当たれば、寄与の方法として正当であるといえます。
財産の維持又は増加についての特別の寄与の要件
加えて、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」が必要です。
要するに、次の3点のすべてを満たさなければなりません。
- 被相続人の財産の維持又は増加があったこと
- 寄与行為と財産の維持又は増加の間に因果関係があること(寄与行為のお陰で財産が維持し又は増加したといえること)
- 「特別の」寄与であること
この中で、最も判断が難しいのは特別の寄与であったといえるかどうかという点です。
この点は、個別具体的な判断になるので、「この要件を満たせばOK」というものではありませんが、一つ言えることとしては、特別の寄与といえるためには、少なくとも、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える寄与が必要であるということです。
被相続人と相続人の間柄が、夫婦であれば協力扶助義務が、直系血族(親子や祖父母等)や兄弟姉妹であれば扶助義務が、同居親族であれば互助義務がそれぞれ存在します。
寄与分が認められるためには、このような義務の程度や範疇を超えた寄与が必要です。
また、寄与行為が何らかの対価を得て行われていた場合も寄与分は認められないでしょう。
なお、寄与行為の見返りに多少の利益を得ることが許されても、得られた利益よりも寄与の程度が大きく上回っていなければ、寄与分は認められないでしょう。


相続財産以上の寄与分は認められない
各相続人の寄与分を合計しても、相続財産の価額を超えることはありません。
例えば、実際は1,000万円の寄与があったが、被相続人が浪費して500万円しか残っていないというようなケースがありえますが、そのような場合でも、認められる寄与分は500万円のみです。
寄与分は遺贈や死因贈与を控除した後の財産にのみ認められる
寄与分は、遺贈や死因贈与を侵害することはできません。
遺贈とは、遺言によって財産を贈ることで、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことです。
寄与分は遺贈や死因贈与を侵害することができないとはどういうことか説明します。
例えば、3,000万円の相続財産があり、そのうち2,000万円が遺贈(または死因贈与)されたとします。
そのような場合は、仮に1,000万円を超える額の寄与があったとしても、主張できる寄与分は、相続財産3,000万円から遺贈(または死因贈与)分の2,000万円を差し引いた残額の1,000万円のみということになります。
寄与分を遺言で定めることはできない
寄与分は遺言で定めることはできません。
どういうことかというと、例えば、被相続人が老後の面倒を見てくれた相続人に多くの財産を残そうと、「相続人○○の寄与分は○○円とする。」とか「相続人○○の寄与分は相続財産の〇割とする。」というような遺言を残すことが考えられます。
しかし、このような遺言は認められません。優先して財産を渡したい相続人がいる場合は、遺言で寄与分を定めるのではなく、遺贈や贈与によるべきです。
ただし、遺留分侵害請求に対して、寄与分を主張して対抗することはできません。
遺留分とは、遺贈や贈与があった場合でも、被相続人の配偶者や子や親などの相続順位の高い相続人に対して担保される取得分のことです。
例えば相続財産の全額が遺贈または贈与された場合でも、配偶者や子などが一銭も相続財産を取得できないということないように、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対して、一定の取得分を請求できる決まりになっているのです。
遺留分侵害請求に対して、寄与分を主張して対抗することはできないとはどういうことか説明します。
寄与分がある人が、遺贈や贈与によって他の相続人の遺留分を侵害するほどの財産を取得した場合に、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。
そのような場合に、寄与分があることを理由に遺留分侵害請求を退けることができるかという問題が生じますが、結論としては、退けることはできないということになります。


特段の事情がある場合は遺留分を侵害する寄与分も認められる
先ほど、優先して財産を渡したい相続人がいる場合は、遺言で寄与分を定めるのではなく、遺贈や贈与によるべきという説明をしました。
しかし、遺贈や贈与に対しては遺留分侵害請求が認められますが、寄与分に対しては遺留分侵害請求は認められないという違いがあります。
例えば、被相続人の2人の子が相続人の場合、相続財産に対してそれぞれ4分の1の遺留分があります。
寄与分が遺留分を侵害できないのであれば、相続人のいずれかに4分の3を超える寄与分があったとしても、寄与分を主張できるのは、4分の1までということになります。
この点、結論としては、遺留分を侵害する寄与分の主張も可能です。その主張が認められるのは、特段の事情がある場合のみです。
特段の事情とは、相続財産のほとんどを、寄与分を主張する相続人が提供していたような場合です。
例えば、相続人Aが、被相続人の生前に、体の不自由な被相続人のためにバリアフリーのマンションを贈与したとします。
被相続人が亡くなったときに、Aはそのマンション分の寄与分を主張することが考えられます。
そのマンション以外に目ぼしい財産がない場合には、Aの寄与分と他の相続人の遺留分が競合しますが、このように、元々Aが贈与した財産にまで遺留分を優先することは必ずしも妥当な結論といえないでしょう。
このような特段の事情がある場合に備えて、遺留分に寄与分を優先する余地が残されているのです。
もっとも、相続財産に対する寄与分の相場としては、最も多いのは2割から3割の間で、高くても5割程度に留まるため、上記のような特段の事情がない限りは、遺留分を侵害するような高い割合の寄与分が認められることはありません。
寄与分と特別受益が両方あった場合
寄与分と特別受益があった場合の計算方法について説明します。
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
事例
例えば、被相続人にはAとBの2人の子がいたとします。
そして、Aには1,000万円の生前贈与を行っており、また、相続財産の価額は2,000万円であったとします。
この場合における特別受益の持戻し後のA、Bそれぞれの相続分は次の式で計算することができます。
- Bの相続分:(2,000万円+1,000万円)÷2=1,500万円
- Aの相続分:1,500万円-1,000万円=500万円
特別受益者と寄与者が同一人であることもあります。
その場合は、まず、特別受益の価額を控除し、それから寄与分の価額を加えます。
この計算順序は、特別受益の価額が、現実の相続財産による相続分の価額を上回る場合に生きてきます。
特別受益の価額が現実の相続財産による相続分の価額を上回っても、マイナスにならないためです。
どういうことか、例を基に説明します。
特別受益者と寄与者が同一人であるときの事例
先ほどの例で、Aの特別受益が2,000万円の場合の最終的な相続分は次のように計算することができます。
まず、現実の相続財産2,000万円に特別受益の2,000万円を加え、寄与分の1,000万円を差し引きます。
そうすると、みなし相続財産は、3,000万円になります。
3,000万円をAとBの2人の相続人で分けると、1,500万円ずつになります。
Aは特別受益が2,000万円あるので、1,500万円から2,000万円を差し引きます。
そうすると、マイナス500万円になりますが、いくら特別受益があってもマイナスにはならない決まりなので、この時点では、Aの相続分はゼロになります。
Bの相続分は1,500万円のはずでしたが、実際に分配することができる相続財産は、現実の相続財産2,000万円から寄与分1,000万円を差し引いて1,000万円なので、Bの相続分は1,000万円になります。
そして、Aには1,000万円の寄与分があるので、Aの相続額も1,000万円になります。
寄与分の時効は?
寄与分には時効がありません。遺留分のような権利もありません。そのため、請求できるのは遺産分割の話がまとまるまでと考えましょう。
特別寄与料には期限あり!
特別寄与料は、民法改正により2019年7月1日から導入された制度です。
相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人を特別寄与者といい、その寄与に応じた金銭の価額を特別寄与料といいます。
特別の寄与をした者が相続の開始および相続人を知った日から6ヵ月、又は相続開始の時から一年を経過したときは請求することができなくなります。
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
まとめ
寄与分の主張の仕方は難しく、認められるにはハードルが高いものです。
お世話になった方へ自分の財産を渡すことでお礼の気持ちを表したいという方もいると思います。
自分の死後、確実に渡したい場合は、遺贈という手段を取ることができます。それには法的に有効な遺言書を作成することで確実性が増すので検討してみてください。
相続費用見積ガイドでは遺言書の作成に強い専門家へ無料で見積りを依頼することができます。
是非ご活用ください。


ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら