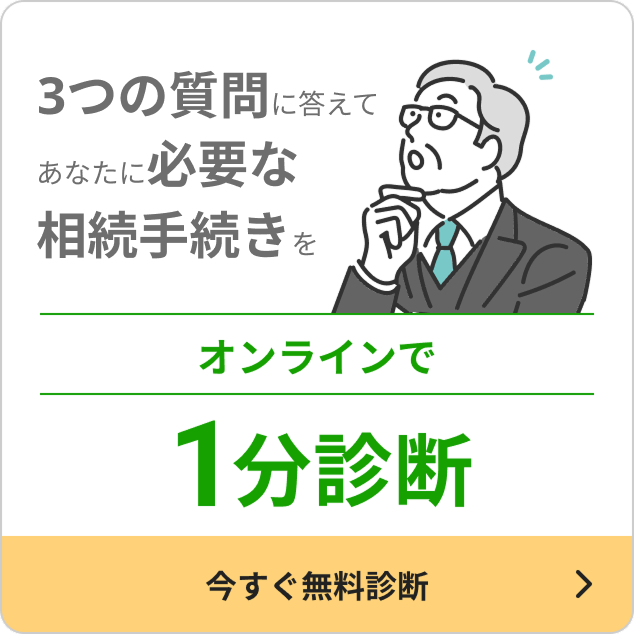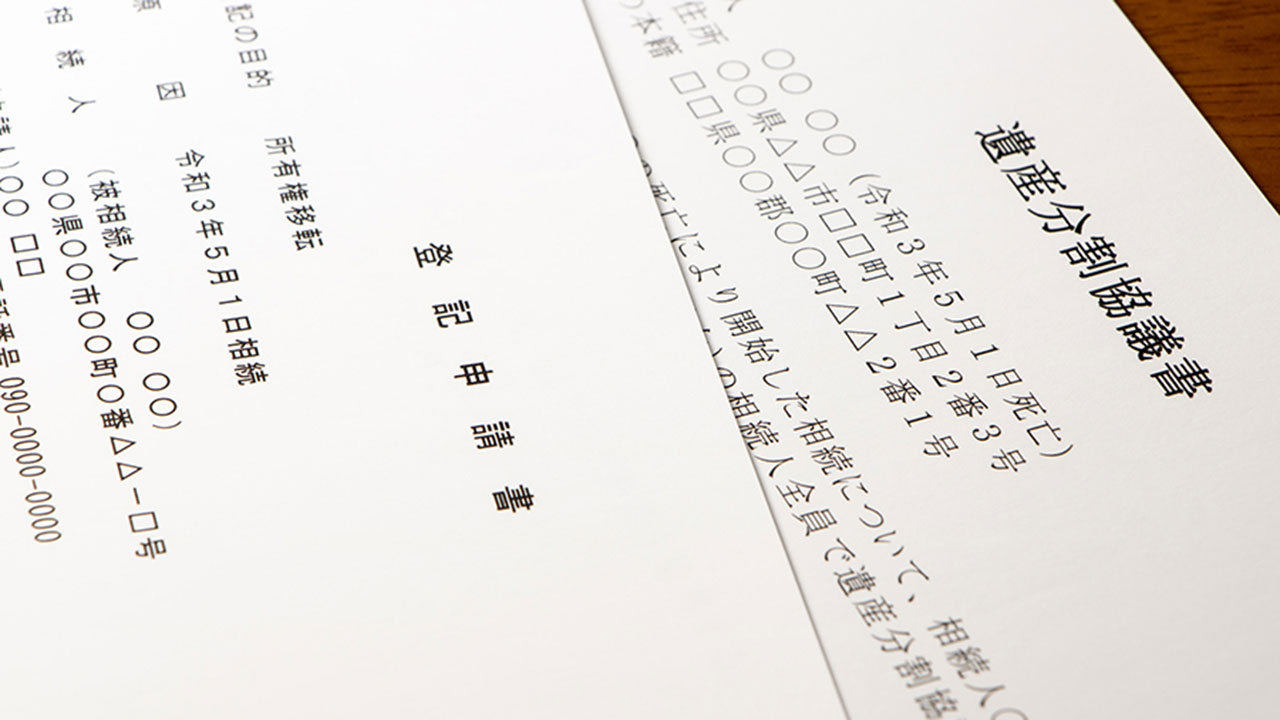暦年課税とは?相続時精算課税とは?生前贈与はどちらがお得?
更新日


親や祖父母などから財産を贈与されたとき、気になるのは贈与税。贈与税は原則として、暦年課税という課税方式を採用しています。一方、場合によっては相続時精算課税という方式も利用することができます。暦年課税方式であれば、年間110万円の基礎控除があるため、それ以下であれば贈与税はかかりません。
しかし、近年、毎年のように税制改正により贈与税や相続税の改正がおこなわれています。
今回は暦年課税方式について、基礎控除や相続時精算課税との違いなども合わせて最新の情報を紹介します。
目次
暦年課税の読み方
暦年課税は、「れきねんかぜい」と読みます。
この場合の暦年とは、1月~12月までの1年という意味です。
4月~3月までの年度における1年と区別するために、1月~12月までの1年のことを暦年と言うことがあるのです。
暦年課税とは? どういう制度?
暦年課税とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。
暦年課税は、贈与者(贈与した人)についても、受贈者(贈与を受けた人)についても制限はなく、誰でも利用できる制度です。
贈与財産の種類にも制限がなく、現金や預貯金、有価証券、不動産などのあらゆる財産の贈与が暦年課税の対象となります。
財産を贈与された場合だけでなく、債務の免除を受けたり、市場価格よりも著しく低廉な価格で物を売ってもらったりした場合も、享受した経済的利益について暦年課税の対象となります。
ただし、法人からの贈与により取得した財産や、扶養義務者からもらった生活費や教育費は、贈与税はかからず、暦年課税の対象とはなりません(法人からの贈与は所得税が課せられます)。
贈与税がかからない場合について詳しくは、国税庁ウェブサイトの贈与税がかからない場合をご参照ください。
なお、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の対象となりません。
相続時精算課税について、詳しくは後述します。
暦年課税の基礎控除
暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。
贈与には贈与税が課税されますが、贈与税は課税価格(贈与税の課税対象となる1年間に受けた贈与の総額)から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。
ですので、年間110万円までは、贈与を受けても贈与税が課されません。また、110万円を超えた場合は、その超えた分に対してのみ贈与税が課されます。
なお、贈与税を納める義務があるのは受贈者です。ですので、基礎控除は贈与者ではなく受贈者について設定されています。
つまり、複数人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額は年間110万円で変わりません。
暦年課税による贈与税の計算方法
暦年課税による贈与税の計算方法は、次の手順で行います。
- 贈与額を合計する
- 基礎控除を差し引く
- 税率を掛けて贈与税を計算する
以下、それぞれについて説明します。
贈与額を合計する
まず、その年の1月~12月に受けた贈与財産の価額を合計します。
基礎控除を差し引く
年間の贈与財産の価額を合計した課税価格から基礎控除の110万円を差し引きます。
税率を掛けて贈与税を計算する
贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産とで異なり、特例贈与財産の方が税率が低く設定されています。
以下では、一般贈与財産、特例贈与財産について、それぞれ説明します。
一般贈与財産
一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない財産のことで、例えば、次の間柄の贈与に使用します。
- 夫婦
- 兄弟
- 子が未成年者の親子
一般贈与財産の税率は下表のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、基礎控除後の課税価格が300万円の場合は、次の式によって、贈与税額を計算することができます。
300万円 × 15% - 10万円 = 35万円
特例贈与財産
一方、特例贈与財産とは、直系尊属(親や祖父母等)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与財産のことです。
なお、配偶者の直系尊属からの贈与には適用できません。
特別贈与財産の税率は下表のとおりです。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 415万円 |
| 3000万円超 | 55% | 640万円 |
節税目的の名ばかり贈与は認められない?
暦年課税に基礎控除があることによって、非課税で110万円×年数分の贈与が受けられることになります。
ただし、毎年110万円ずつ贈与しても、実態として1つの贈与であれば、毎年の基礎控除を適用することはできません。
例えば、毎年110万円ずつ、20年間にわたって贈与を行えば、110万円×20年=2200万円を非課税で贈与できるように思われます。
しかし、20年にわたって110万円ずつ贈与することが初めから約束されているような場合は、その約束した年にまとめて、(2200万円-110万円)×50%-250万円=795万円の贈与税が課税される可能性があります(なお、一般贈与財産として計算しました。)。
このようにまとめて課税されることを避けるためには、どのように対策すればよいでしょうか?
ウェブ上では、実に様々な対策が見受けられます。
例えば、毎年入金する日を変更するとか、金額を変更するとか、たまには基礎控除の枠を超えて贈与して贈与税を申告するとか、毎年契約書を作成するとか、毎年贈与式を行い写真を残すとか、様々な対策の必要性が声高に叫ばれています。
一番問題となるのは、贈与者が受贈者名義の口座を管理しているようなケースです。
贈与契約が成立するには、贈与者の贈与する意思と、受贈者の贈与を受ける意思が合致していなければなりません。
そのため、親が子に内緒で、子名義の銀行口座を開設し、毎年入金しているような場合は、意思の合致がないので、贈与は成立していません。これを名義預金といいます。
また、親が入金していることを子が知っていて、贈与について承諾していた場合は、贈与契約は成立しているものの、税務上は、贈与者が口座を管理している場合は、毎年110万円ずつ入金していても、毎年の贈与が成立しているとは認められず、受贈者に通帳と届印を渡して、管理を任せた時点で、贈与が行われたと認定され、その年にまとめて課税されるおそれがあります。
毎年贈与したと税務上認められ、暦年課税の基礎控除を活用するためには、次のような対策が有効であると考えられます。ただしこれらを行ったからといって必ず贈与の実態があったことが立証できるということを保証するものではありません。
- 受贈者自身が開設した受贈者名義の口座に、贈与者名義の口座から振り込む
- 受贈するための口座は、受贈者が管理し、受贈者が自由に出金して使用できる状態にしておく(通帳、届印、キャッシュカード等は受贈者が管理する)
- 贈与契約書を毎年作成する。
- 110万円を超える贈与があった年は、当然ながら税務申告を行う
- 有価証券を贈与した場合は、速やかに名義変更を行う
- 不動産を贈与した場合は、速やかに所有権移転登記を行う
暦年課税の贈与に相続税が課される場合(相続開始前3年以内の贈与)
暦年課税の場合は、原則としては、相続税はかかりません。
しかし、相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の3年間※に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます。(令和6年より7年間に改正予定、詳細は後述)
既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の2重課税となってしまいます。そこで、相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
ちなみに、住宅取得等資金の贈与の特例を利用しての贈与の場合は、亡くなる前3年以内の贈与であっても、贈与税非課税とされた金額については相続税も非課税となります。(足し戻しの計算は行なわれません。住宅取得等資金の贈与の特例については関連記事をご覧ください)。
令和5年度税制改正では3年が7年に!
亡くなる前の3年間に行われた贈与の持ち戻しについて、令和5年度の税制改正大綱によると、令和6年1月以降は生前贈与の持ち戻し期間が7年へ改正されます。
詳細については、「令和5年度税制改正の生前贈与加算と相続時精算課税・暦年贈与の節税方法を解説」を参照してください。
暦年課税の申告方法
暦年課税の申告方法について説明します。
申告が必要な場合
1月~12月の1年間に基礎控除額(110万円)を超える贈与を受けた人が対象です。
なお、配偶者控除や住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けて非課税となる場合であっても申告は必要です。
申告時期
暦年課税の申告時期は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。
期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が課せられる可能性もあるため、期限内に申告するようにしましょう。
申告場所
住所地を管轄する税務署で行います。
なお、税務署では、申告に関する相談にも応じているので、不明な点は問い合わせるとよいでしょう。
申告書類の作成方法
申告書類の作成方法については、国税庁ウェブサイトの「贈与税申告のしかた」をご参照ください。
相続時精算課税とは?
贈与税は暦年課税が原則ですが、相続時精算課税を選択することもできます。
以下、相続時精算課税について説明します。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税制度とは、親や祖父母から贈与された財産の価額が、2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
この説明だけだと大変お得な制度に思えます。
しかし、贈与税は控除されますが、相続時には、相続時精算課税適用財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税が課税されるので注意が必要です。
相続時には、他の遺産と合算して相続税の対象となるのです。
誰から誰の贈与のときに選択できる?
次の条件のすべてを満たす場合は、制度を利用することができます。
- 贈与者が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上
- 受贈者(贈与を受ける人)が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
- 贈与者と受贈者の関係が親子か祖父母と孫
この条件を満たさない場合は、相続時精算課税を選択することはできませんから、暦年課税で納税するしかありません。
また、相続時精算課税は受贈者が贈与者ごとに選択することができます。
ですので、例えば、父からの贈与は暦年課税(通常の課税方式)にして、母からの贈与は相続時精算課税にするということも可能です。
ただし、相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。
どんな財産でも大丈夫?財産の種類に決まりはある?
贈与財産の種類には制限はありません。
贈与する財産の価額に決まりはある?
金額に制限はありませんが、控除されるのは贈与者ごとに2500万円までです。
1億円の不動産の贈与の際に、相続時精算課税制度を利用した場合は、7500万円については贈与税を支払わなければなりません。
2500万円を超えた分の贈与には、一律20%の贈与税が課されます。
課された贈与税は、相続時精算課税の際に、相続税から控除されます。
贈与税額が相続税額を上回る場合は、差額の還付を受けることができます。
相続時精算課税のデメリット
相続時精算課税のデメリットには、次の3つが考えられます。
- 贈与税の非課税枠(毎年110万円)がその年以降ずっと使えなくなる
- 財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる
- 申告の手間が生じる
以下、それぞれについて説明します。
贈与税の非課税枠(毎年110万円)がその年以降ずっと使えなくなる
繰り返しになりますが、贈与税は暦年課税の場合は、年間110万円までは非課税ですが、相続時精算課税を選択した場合は、その選択した贈与者からの贈与は、その年以降すべて相続時精算課税となり、110万円の非課税枠を利用することはできなくなります。
しかし、令和6年より2500万円以外に毎年110万円ずつ贈与していても非課税で申告不要となり、子のデメリットは事実上デメリットではなくなるでしょう。
▶令和5年度税制改正の生前贈与加算と相続時精算課税・暦年贈与の節税方法を解説
財産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合は税金が高くなる
財産総額が、相続税の基礎控除額を上回る場合は、相続時精算課税制度を利用しない方が節税になるケースも多いです。
相続税にしても贈与税にしても、累進課税といって課税額が大きくなればなるほど税率が高くなる仕組みを採用しています。
贈与税は暦年課税の場合は毎年課税されるので、小分けにして毎年贈与していったほうが、税率を低く抑えることできる場合があるのです。
申告の手間が生じる
相続時精算課税制度を選択した場合、選択した贈与者から贈与を受けた年は金額にかかわらず申告が必要となり、手間がかかります。
しかし、相続時精算課税の利用推進の観点から、徐々に利便性を高くする方向です。先述の相続時精算課税選択した際、110万円までは非課税で申告が不要になる新しい仕組みが盛り込まれたのもその表れといえます。
▶令和5年度税制改正の生前贈与加算と相続時精算課税・暦年贈与の節税方法を解説
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得?
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを利用した方が得かどうかは、相続税の基礎控除内に財産総額が収まるかどうかという点が重要な判断基準となります。
ですので、相続税の基礎控除の計算方法について説明します。
贈与税の控除額は年間110万円でしたが、相続税の基礎控除額はそれよりもずっと多く、次の式で計算されます。
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです。
贈与者の財産総額(贈与財産だけでなく相続予定の財産も含めた財産総額)が、相続税の基礎控除の枠内に収まるかどうか計算し、収まらなさそうなら相続時精算課税と暦年課税どちらが特になるかを比べます。その際、亡くなる前の3年間(令和6年より7年間となる予定)に行われた贈与の持ち戻しについても併せて検討しましょう。
もっとも、正確に見積もるには、緻密な計算が必要ですので、相続に強い税理士に相談するとよいでしょう。
相続費用見積ガイドでは、無料で複数の税理士に費用の見積りを依頼することができます。是非ご活用ください。


本記事の内容は、遺産相続弁護士ガイドの記事を、原則、記事執筆日(2023年2月22日)時点の法令・制度等に基づき再編集しています。最新の法令等につきましては、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家等にご確認ください。なお、万が一記事により損害が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら