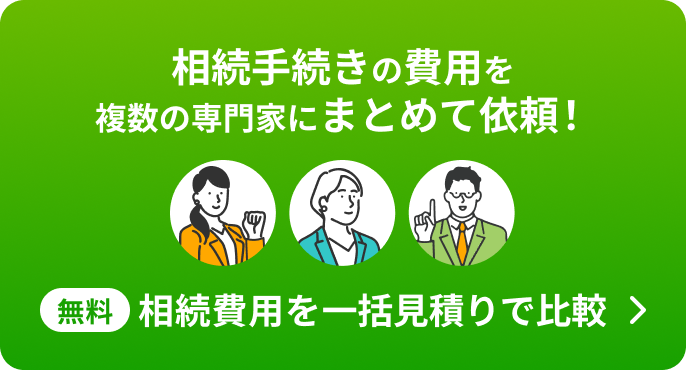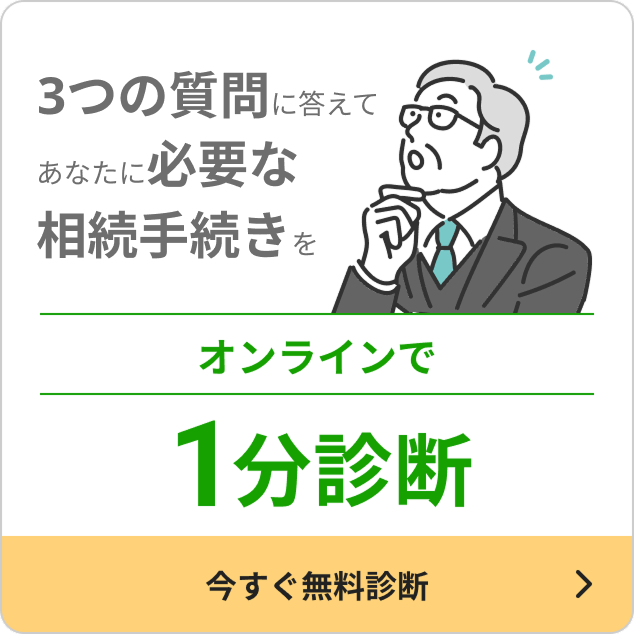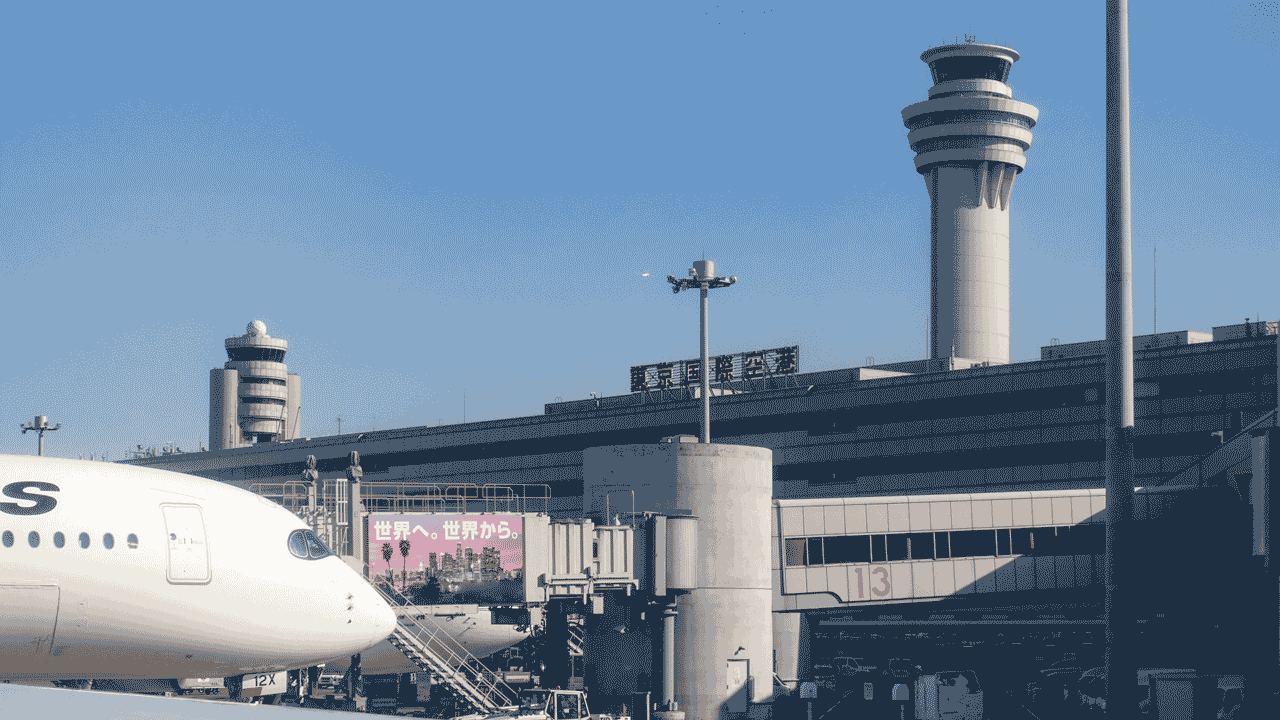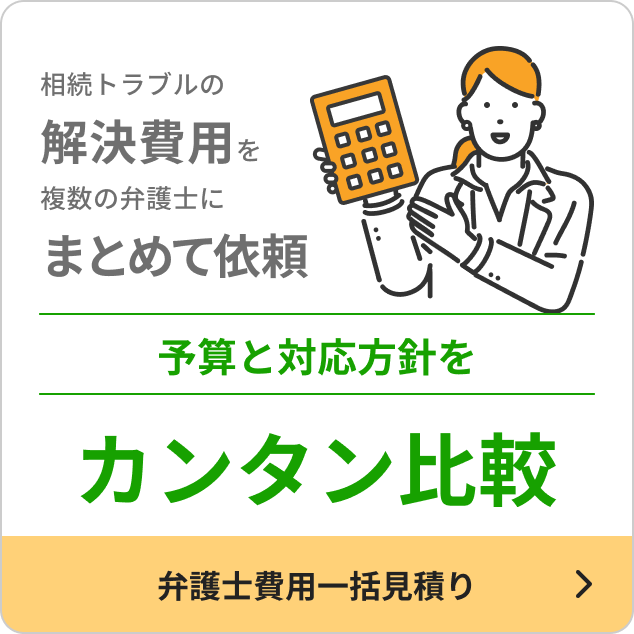遺産分割協議書を自分で作成して法務局で相続登記をするための知識
更新日
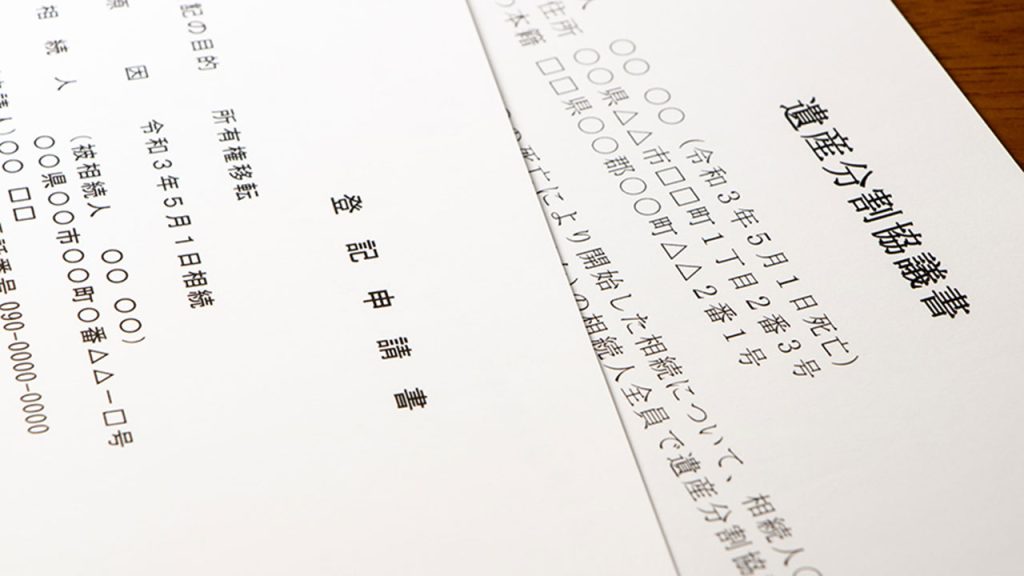
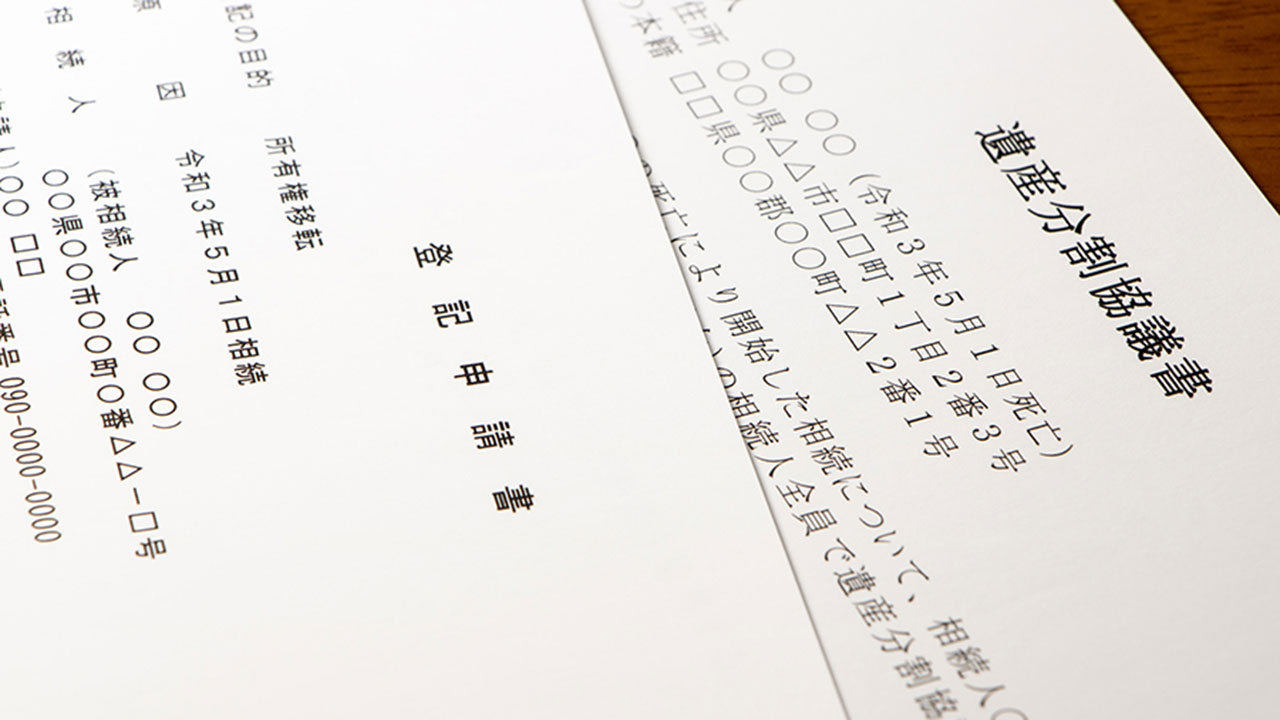
相続財産に不動産がある場合、相続したときは法務局での相続登記が必要です。
そのためにはまず、故人の遺産をどのように分割するか遺産分割協議をおこない、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は銀行解約や相続登記、相続税申告などの手続きに必要となるため、多くの場合で作成しておかなければなりません。
この記事では、相続登記のための遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を法務局に提出するための知識について説明します。
相続登記は2024年4月1日より義務化されました。登記せずに放置するとペナルティが課される可能性があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、相続登記の手続きが必要です。登記申請の際に、登記原因証明情報として遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を添付しなければなりません。
この記事のポイント:
- 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、それぞれ利用すべきケースが異なる
- 遺産分割協議による所有権移転登記には、遺産分割協議書が必要
- 所有権移転登記には、登記申請書のほか被相続人や相続人全員の戸籍謄本が必要
相続登記については、「【徹底解説】相続登記の手続きと必要書類、早めに相続登記した方が良い理由【司法書士監修】」を参考にしてください。
相続登記の義務化については、「【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化が決定!違反の場合は過料も」を参考にしてください。
目次
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、その人の死亡と同時にもらい受ける権利のある人が複数いる場合に、その人たちの間で遺産を分けることです。
遺産分割は、相続人等の遺産を受け取る権利がある人が複数いて、かつ、遺言によってすべての財産の処分(受取先)が決まっていない場合に必要です。
遺産分割を受ける権利を持っているのは、次のいずれかに該当する人です。
- 共同相続人
- 包括受遺者
- 相続分譲受人
共同相続人
共同相続人とは、法定相続人(民法の定めにより相続人となる人)が複数人いる場合に、遺産分割前の相続財産を共有している状態の相続人のことです。
包括受遺者
包括受遺者とは、包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、遺贈(遺言によって財産を贈られること)の対象となる財産を特定せずに、積極財産(プラスの財産)も負債などの消極財産(マイナスの財産)も包括的に承継する遺贈(包括遺贈)を受けた人のことです。
相続分譲受人
相続分譲受人(そうぞくぶん ゆずりうけにん)とは、相続人から、その相続分を譲り受けた人のことです。


遺産分割協議とは?
遺産分割にあたって遺産の分け方を決めるために行う協議のことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。遺産分割協議書は銀行解約や相続登記、車の名義変更などの相続手続きで必要です。
ただし遺言書がある場合は、相続手続きに遺産分割協議書が不要となることも。遺言は法定相続より優先されます。手続きによって必要書類は異なるので、その手続きをする機関に問合せてみてください。


遺産分割協議証明書とは?
遺産分割協議証明書も、遺産分割協議書と同様、遺産分割の結果を書面にしたもので、遺産分割証明書と呼ばれることもあります。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違いは、各遺産の取得者が個別に証明するものが遺産分割協議証明書、すべての相続人がまとめて証明するものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議証明書について詳しくは「遺産分割協議証明書とは?メリットデメリットや遺産分割協議証明書との違い、書き方の見本付き【行政書士監修】」をご参照ください。
遺産分割が不要な場合はある?
遺産分割協議書が不要の場合もあります。それは遺産を受け取る権利がある人が1人以下しかいないか、または、遺産を受け取る権利のある人が複数いたとしても遺言によってすべての財産の処分(受取先)が決まっている場合です。 遺言書がある場合、相続手続きの際には遺言書を提出します。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書、それぞれを利用すべきケース
相続人が近くに住んでいる場合は、全員が一堂に会して遺産分割協議書に署名・押印することができるので、このような場合は、遺産分割協議書が適しています。相続人全員が集まることができない場合は、郵送等で各相続人に順次回していき、署名・押印を集めることもできます。
相続人の数が多いと、全員の署名・押印が終わるまでに日数がかかるでしょうし、途中で紛失することもあるでしょう。
この点、遺産分割協議証明書の場合は、各相続人が個別に署名・押印することができるので、遺産分割協議書の場合よりも日数が短縮できることが期待できますし、途中で紛失されて一からやり直しということもありません。
したがって、相続人の数が多く、かつ、散り散りに住んでいる場合は、遺産分割協議書よりも遺産分割協議証明書の方が便利であるといえます。
しかし、遺産分割協議証明書にも欠点があります。
遺産分割協議書の場合は、各相続人がそれぞれ原本を1通ずつ持ちますが、遺産分割協議証明書の場合は、基本的には代表者しか原本を持ちません。
後述の通り、遺産分割協議証明書や遺産分割協議書は、相続手続に用いるものです。
一人が代表してすべての相続手続を行う場合は、遺産分割協議証明書で問題ありませんが、それぞれが相続手続を行うのであれば、遺産分割協議書の方が便利でしょう。
遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を法務局に提出するとき
遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を法務局に提出するのは、遺産分割によって不動産を取得した人が、その不動産の所有権移転登記をするときです。 相続登記は、通常、司法書士に依頼しますが、自分で行うことも可能です。
相続登記の申請は、その相続不動産を管轄する法務局で行います。 全国の法務局とその管轄エリアは、法務局の「管轄のご案内」ページで確認することできます。
登記には登記原因証明情報が必要ですが、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)等が登記原因証明情報となります。
「相続登記を自分でやる時間がない」「自分でやろうと思ったけど方法がわからない」という方は、司法書士に相談することをおすすめします。
相続費用見積ガイドでは相続に強い司法書士から一括見積を取ることができますので、ぜひご利用ください。


登記申請のための遺産分割協議書のひな形
遺産分割協議書の様式に決まった様式はありません。
縦書きでも横書きでも構いませんし、パソコンで作成しても手書きで作成しても、いずれでも問題ありません。
すべての相続財産に対して誰がどれだけ相続するのかを記載します。
主な決まり事としては、遺産分割を受ける権利を持っている人(共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人)の氏名・住所を記載し全員が押印するということと、複数枚に及んだ場合はページのつなぎ目に契印を押すということが挙げられます。
法務局のホームページでは所有権移転登記申請書に添付する遺産分割協議書の記入例が公開されていますのでぜひ参考にしてください。


遺産分割協議による所有権移転登記に必要な書類
遺産分割協議による所有権移転登記には次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 登記する不動産を取得する相続人の住民票
- 最新年度の固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
なお、法定相続情報証明制度を利用する場合は、上記の1〜3の書類は不要です。
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。
提出書類の原本を還付してもらう方法
提出書類の原本を還付(戻してもらう)してもらう方法には、次の2つがあります。
- コピーを所定の方式にのっとって併せて提出する
- 相続関係説明図を添付する
以下、それぞれについて説明します。
コピーを所定の方式にのっとって提出する
コピーを所定の方式にのっとって提出することによって、前述の1〜7のすべての書類の原本の還付を受けることができます。コピーした書類の空いたスペースに「この写しの内容は原本と相違ありません。」と書き、署名(または記名)押印をします。
この押印は登記申請書に押印した印鑑でしなければなりません。
すべてのコピーに上記の文言を書くのは大変なので、1枚だけに書いて、それぞれの書類の間に契印(割り印)をしても構いません。
相続関係説明図を添付する
相続関係説明図を添付することによって前述の1と3(以下に再掲)の原本の還付を受けることできます。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
相続関係説明図とは、亡くなった人の相続人が誰で、各相続人が亡くなった人とどのような続柄なのかという相続関係を説明するための家系図のような図のことです。
相続関係説明図については「相続関係説明図とは?法定相続情報一覧図との違いや作り方をわかりやすく解説【見本付き】」を参考にしてください。
登記簿附属書類の閲覧方法
遺産分割協議がまだ済んでいないはずなのに所有権移転登記がなされている等、不可解な登記がなされている場合、どのような登記証明情報に基づき登記申請がなされたのか等、登記申請時の附属書類を確認したい場合があります。
そのような場合に、登記申請時の附属書類を確認するには、法務局に登記簿附属書類閲覧申請書を提出して、その閲覧を申請します。
この申請ができるのは、利害関係人のみです。
利害関係人に当たるのは、例えば、法定相続人、包括受遺者、相続分譲受人、その不動産の受遺者、その不動産の受贈者(贈与を受けた人)等が考えられます。
登記簿附属書類閲覧申請書の用紙は法務局で入手することができます。附属書類の閲覧申請ができるのは、登記から30年間です。


遺産分割協議書についてよくある質問
遺産分割協議書についてよく聞かれる質問を集めました。
遺産分割協議証明書とは何ですか?
遺産分割協議証明書も、遺産分割協議書と同様、遺産分割の結果を書面にしたものです。
遺産分割協議書を法務局に提出するのはどんなときですか?
遺産分割協議書を法務局に提出するのは、遺産分割によって不動産を取得した人が、その不動産の所有権移転登記をするときです。
所有権移転登記に必要な書類は何ですか?
遺産分割協議による所有権移転登記には次の書類が必要です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄本、登記する不動産を取得する相続人の住民票、最新年度の固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。
まとめ
以上、遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を法務局に提出する際の知識について説明しました。遺産分割協議書の作成や相続登記などを専門家に相談したい場合は、ぜひ相続費用見積ガイドをご利用ください。


ご希望の地域の専門家を
探す
ご相談される方のお住いの地域、
遠く離れたご実家の近くなど、
ご希望に応じてお選びください。
今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら